” ガーデニングハウス ”を建てています!
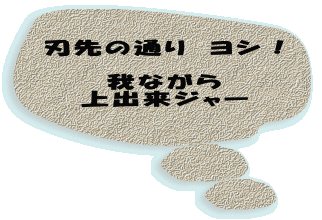
<早い話しが、庭仕事用の物置小屋のこと・・・>
鉋や鑿は、ディァ〜ク(大工)の ” 命 ”
シッカリと研ぎました!。

材料の刻みには時間が掛かる為、
2〜3本づつに小分けして仕入れました!
一部の管柱には、こんな継ぎ方を造って見ました v(^_^)

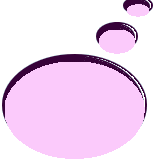


カンナ ノ ミ



ドッコイショっと!これがまた重いんだょな〜
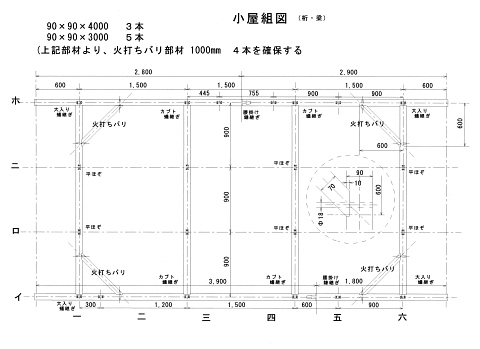
2009年 8月〜


「腰掛け鎌継ぎ」の刻み後の姿です
「大入り蟻継ぎ」を施した部材もあります




まずは、基本となる図面の作成です!
= 工業高校時代は、製図板とT定規だった =
学校での製図の授業(古いなぁ〜)を想い出しながら・・・
今は、パソコンのCadソフトで、スゥ〜イ・スィ !


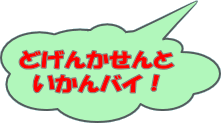
<墨付け画像は、「腰掛け鎌継ぎ」です>
材料の木材を購って運ぶ為の、軽トラックの補助架台も手造りしました。
材木を揃えて、いよいよ部材の刻みです。
2009年10月〜

さぁ〜て
どんなものが出来るか?
お楽しみに・・・
筋かいを組み付ければ、ほぼ出来上がりです。
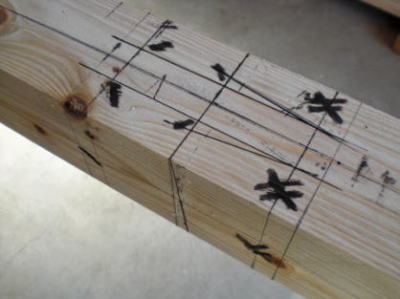


2009年 9月〜
と! 口では簡単に云えますが、
えぇ〜と、ココはどうするんだったっけ・・・・?
歳を取ると、もの忘れがすこぶる良くなった(笑)
困ったもんですなぁ〜 !!
第一期工事(主構造材の加工)が、やっと終りました。 f^_^;
続いて第二期工事(基礎造り)ですが、少々日数を要します。
基礎造り完工まで、小休止です・・・ m(__)m
続きは、また後で〜〜

さぁ〜て、仕上がりは
どうかなぁ〜?


