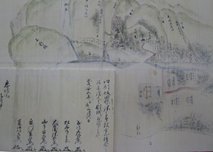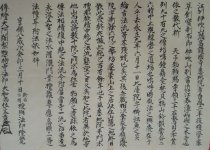| 年 号 |
西 暦 |
記 事 |
| 白鳳2年 |
673年 |
役の行者開山する。 |
| 文武年間 |
697年〜 |
文武天皇の勅願寺となる。 |
| 天平神護 |
746年 |
白山より泰澄入山、再興する。奈良の興福寺に属する。 |
| 仁寿2年 |
852年 |
三修上人入山、寺観が整えられる。 |
| 元慶2年 |
878年 |
定額寺に列せられ寺領三千石鷲目三千貫であったと伝えられている。弥高百坊と称され湖北地方の学問の聖地となり、本院は弥高寺の学頭を務めている。 |
| 正和2年 |
1313年〜 |
後醍醐天皇中宮藤原禧子、御産祈祷所になる。山麓の柏原庄や伊吹庄の地頭佐々木京極類代の庇護を享ける。 |
| 明応8年 |
1499年 |
弥高・観音・太平・長尾護国寺、本末争い対立により宿坊を焼失する。 |
| 永正年間 |
1504年〜 |
佐々木京極氏の内紛、近江守護の頭佐々木六角の湖北征伐に被災する。 |
| 永正9年 |
1512年 |
本堂炎上する。仁和寺や醍醐寺などの真言門跡寺院と関与し十一面千手観音を本尊として安置する。 |
| 永正10年 |
1513年 |
本堂の勧進が行われる。 |
| 天文5年 |
1536年 |
伊福貴社勧進奉加帳には「悉地院源秀」他四十の坊名がみられる。 |
| 天正8年 |
1580年 |
山城として要塞化している。寺域は織田信長の兵火に遭い弥高山西山麓の古弥高に数ヶ寺移転する。 |
| 慶長年間 |
1596年〜 |
彦根藩の提封となっている。彦根藩井伊家より寺領山林が寄進される。彦根北野寺他真言八ヶ寺より金光明最勝王経(唐本)が奉納される。 |
| 寛永6年 |
1629年 |
梵鐘の鋳造が行われる。 |
| 慶安2年 |
1649年 |
弥高山西山麓より移転、現在の地には院家が建てられる。 |
| 貞亨6年 |
1689年 |
弥高山、阿伽井谷の岩窟に開山堂が築かれる。 |
| 元禄5年 |
1692年 |
昌山法師の代に長浜総持寺の客末となり五ヶ院家に遇せられる。大和国長谷寺末となり、真言宗豊山派に属する。 |
| 明和5年 |
1768年 |
旧本堂が現在の地に法印淳諦により、改築再建される。 |
| 明和8年 |
1771年 |
旧庫裏が再建される。 |
| 天明6年 |
1786年 |
鐘楼堂が再建され、宝篋印塔を建てる。 |
| 文化4年 |
1807年 |
寺号碑が建てられる。 |
| 文化7年 |
1810年 |
山門が再建される。 |
| 明治3年 |
1870年 |
神仏分離令等による弾圧が記録されている。 |
| 明治40年 |
1907年 |
再建のための桧を植林する。現在の庫裏に改修する。 |
| 昭和22年 |
1947年 |
農地解放令により、農地の大半を手放す。 |
| 昭和24年 |
1949年 |
第二次世界大戦に供出した梵鐘、半鐘が再鋳造される。 |
| 平成3年 |
1991年 |
桧を伐採して、現在の本堂及び塔中安養院を大改修(新築)落慶する。再び桧を植林する。 |