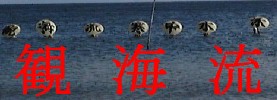21世紀1月14日11時30分 朝から小雪の舞う冷たい日。
阿漕浦海岸で観海流寒中水泳が行われた。
来年で150年を迎える伝統行事。東京、名古屋の他流派の方の出演もあった。
当日の最高気温は5.1℃。フンドシ姿の参加者は寒さに震えながらもすばらしい
演技を見せてくれた。
歩き方
近鉄津新町駅を出て右折する(東側)。
直進し国道23号線に出る。左前は百貨店。
23号線を右折。岩田橋を渡り直ぐ左折(東側)。
右側に津市体育館がある。直進すると通称近鉄道路と交差する。
左側には電車の鉄橋をそのまま道路にしたのがはっきり分かる橋がある。
歩くのは、もう少し直進。
伊勢湾海洋スポーツセンターが見える。通称ヨットハーバー。
この海岸に観海流流祖宮初太郎像がある。
海洋スポーツセンター付近は魚釣り場でもあり、休日は多くの太公望がいる。
海浜交通公園もあり、自転車の貸し出しがある。
季節、季節での海の遊びには最良の場所である。
海洋スポーツセンタ-には宿泊設備、食堂等がある。
観海流寒中水泳大会は毎年1月初めに行われる。
平成13年は1月14日に実施した。
写真撮影は2001年1月14日
|
 |
|

|
|
|
宮 発太郎の像
|
| 初泳ぎの儀(海の安全祈願) |
|
|

|
|

|
|

|
|

|
|
| 泳者の準備運動 |
| 観 衆(は寒い) |
| 弓 矢 術
立泳ぎで矢を射る |
| 番傘による
寒中水泳 |
|

|
|

|
|

|
|

|
|
| 扇子使用の泳ぎ |
| 抜き手の技 |
| 抜き手の技 |
| 水 書 |
|
| 水 書 中 |
|

|
|

|
|

|
|
| (連続ですよ) |
| 祝 |
| 21 世 |
| 紀 |
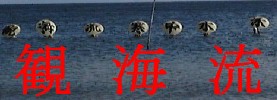
|
「観海如陸 心水一致」
津藩家老藤堂高克公は、武州忍藩(現埼玉県行田市)の浪人、”
宮 発太郎”の泳法を見て”海を観る事、陸の如し”と感心した。
これが観海流の始まりである。
発太郎は武術修行のため紀州藩等諸国を遊歴中に水練の独自の技を習得した。
時は嘉永5年(1852)、藤堂藩に来藩した発太郎は泳法を披露。
伊勢湾の防衛が必要だった藤堂藩は有益な泳法として、藩校有造館
の武道教科に採用した。
発太郎は藤堂藩を去るが、藩士山田省助、種村順次郎兄弟に免許皆伝を与え、省助は初代家元
になった。
安政3年(1856)の事である。省助は明治3年(1870)津藩の水泳教師に採用され、阿漕浦に道場を開設
、多くの門徒を養成した。
二代目家元、熊之進は北海道に支部を作るとともに、海軍江田島の水泳教師として、
海軍泳法として観海流は全国に広まった。
大正12年(1923)岩田川で寒中水泳をはじめると共に、他流派と交流。
昭和5年には、極東選手権大会で、昭和39年には東京オリンピックで泳法を披露(3代目家元)
した。
その間、昭和29年には観海流100周年を記念して阿漕浦に石像を建立、知多半島の常滑迄の遠泳を
おこなった。
昭和32年三代目家元山田慶介は津市無形文化財の指定を受ける。
昭和47年(1972)現在の家元、山田謙夫氏が4代目家元を継承し、
新世紀への技術の伝承を行っている。
・昭和48年:全国高校総体で公開演技。遠泳(津ー常滑)
・昭和50年:30回国民体育大会(みえ大会)で公開演技
・昭和51年:第2回汎太平洋シンクロナイズド・スイミング国際大会で公開演技。
・平成 元年:津市市制100年協賛事業で日本泳法全国大会を開催
・平成 7年:第44回日本泳法研究会で発表。資料集「観海流」刊行
・平成10年:第12回津ベストシチズン賞受賞
又市内のスイミングクラブで教室を開き技術の伝承に努めている。
基本はカエル泳法。「波を立てずに静かに目的地に向かって真っ直ぐ泳ぐのがポイント」との事。
橋北・橋内・橋南地区へ戻る
イベント紹介へ