 パームトップアンプ?
パームトップアンプ?5687SEPP QRPアンプ
 パームトップアンプ?
パームトップアンプ?
12B4A SEPPミニアンプを作り始めてからしばらくして、手作り真空管アンプのページのオーディオ掲示板(関西)でQRPアンプの話題が持ち上がり、私はこれに大変興味を持ちました。 手作り真空管アンプのページではQRPアンプの分科会もできています。 私が手掛てきた一連の1Wクラスのミニアンプの考え方は、このQRPアンプのそれと似通っているようです。 残念なのは私の考えていたミニアンプの基準と手作りアンプの会のQRPの基準とは少し違いがあることで、私の作ったミニアンプの中でQRPアンプの基準を満たしているものはありません。
12B4Aアンプはシャーシの加工を残して殆ど出来上がったのに、待てど暮らせど注文した出力トランスが入ってこないという日が続きました。 バラック状態ではありますがアンプは動いている状態でしたので、何とか音を出したいと考えて、代わりになるトランス(600Ω:8Ω)を求めて日本橋へ出かけました。 そこで見つけたのが山水のトランジスタ用トランスのST−48(@475円)です。 これは重量わずか59gの小さなトランスです。 小さくても音を出すことくらいは何とか出来るだろうと、あまり期待をせずに買ってきたのですが案外まともな音が出ました。 このトランスは12B4Aアンプを組み上げたら必要がなくなるので、これを使ってQRPアンプを作ることにしました。
手作りアンプの会のQRPアンプの基準は、シングルアンプの場合は(出力段の?)プレート損失が5W以下、プッシュプルアンプは8W以下の複合管ということのようです。出力については特に規定は無いようです。 私はというと、1W前後の出力とコンパクトに作るということがミニアンプの要件と考えていましたので随分と違います。 個人的にはプレート損失で基準を作るというのはあまり意味を持たないのではないかと思っていますし、なぜ複合管なのか?という疑問もあるのですが、手作りアンプの会の考え方には、ごく一般に使用される真空管を排除して、普段はあまり使われることのない球や、せいぜいドライブ段までに使われて出力管としては取り上げられることは殆ど無い球などにスポットを当てようという意図があるように思われます。
本機は12B4A SEPPアンプと回路をほぼ同じにし、QRPアンプの基準に合う球を使用し、出来るだけ安価に、コンパクトに製作するということに的を絞りました。 12B4Aアンプはそれなりにお金を掛けたアンプですから、面白い対比になると思います。
両ユニットのプレート損失が合計8W以下の複合管で、600Ωの負荷をドライブ可能な内部抵抗の低い球は無いかと探してみましたが、残念ながら見当たりませんでした。 できればrpが1kΩ以下の球が理想的なのですが、もしかすると存在しないのかも知れません。幸いST−48には4Ωタップがあるので、これに8Ωを接続して見かけ1.2kΩ(実測で約1kΩ at1kHz)のマッチングトランスとして使うことで、5687、7044、7119あたりの球が浮上してきました。 出来るだけ安価に済ませるということで、手持ちの球の活用という事にして5687WBを選択しました。 この球でゼロバイアスの時に大体1.5kΩくらいの内部抵抗ですからちょっと苦しそうですが、まあ何とか使えるかなという所です。 5687WBは、3者の中でもいちばん小柄なのでQRPアンプに向いてるような気がします。
 横に見えるのは調整窓です。
横に見えるのは調整窓です。
回路図
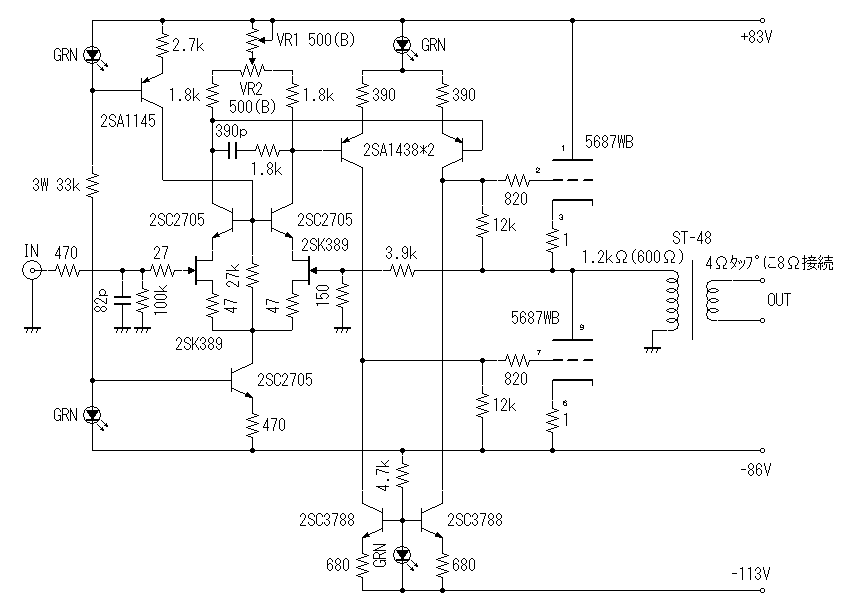
アンプ部の回路は6C19P SEPPアンプとほぼ同じ構成です。 調整の方法などは6C19Pアンプのページをご参照下さい。 コンパクトに作り上げるため、前段各部の電流は出来るだけ小さく設計しました。 出力段のアイドリング電流は20mAとし、A級動作させています。 出力トランスはオートトランスの6C19Pアンプと違い、絶縁トランスですので本機ではDCサーボ回路は採用しませんでした。 アイドリング電流およびDC電位調整後のアンプ部の出力(出力トランスの1次側)は、電源投入直後には0.3V程度の直流電圧が発生しますが暫くすると収まり、以降±数mV程度をふらふらと漂います。 出力トランスの1次側のDC抵抗は34.5Ωありますから、特に問題は無いと思います。
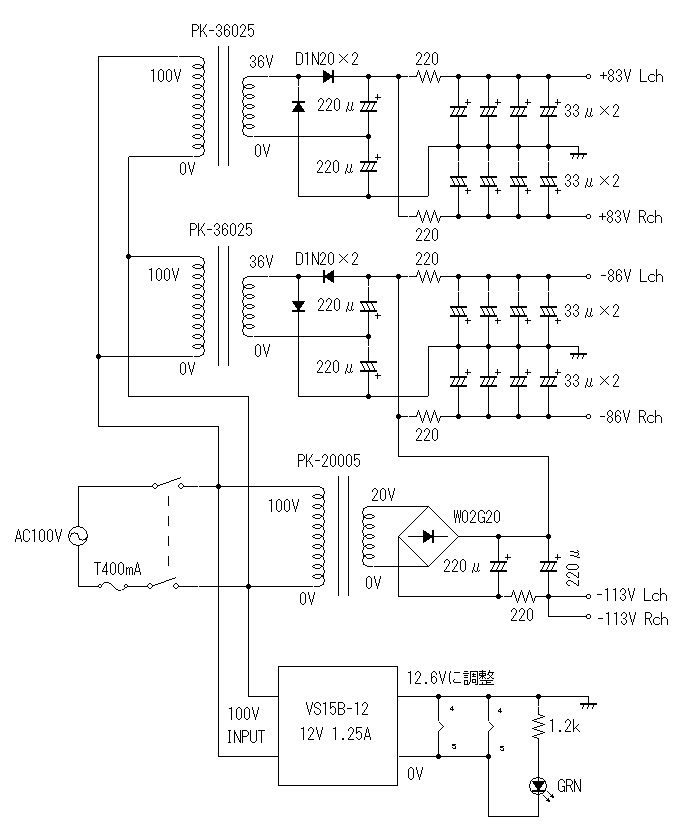
電源については12B4Aアンプのように特注の電源トランスを使うなんて事は、QRPアンプではご法度でしょう。 出力トランスがトランジスタ用なので、電源トランスもごく一般的に入手できるトランジスタ用のものを選択しました。 SEL製のPCB用ピン端子タイプで36V、0.25Aのものを2つ倍電圧整流して±B電源を、20V、0.05Aのもので出力段のマイナス側のバイアス電源を作っています。 B電源用に使っているトランスは+側と−側で電圧が少し違いました。ばらつきでしょうか?また、レギュレーションも良くありません。 出力段をA級動作させているのもレギュレーションが良くないことが理由の一つです。 ヒータートランスまでシャーシに入りそうになかったので、悩んだ挙句、ヒーターにはスイッチング電源を使いました。 スペースの関係で採用したスイッチング電源でしたが、後述のとおり発熱が大きく、スイッチング電源特有のノイズがアンプの残留ノイズの波形に出てくるなど、できればもうひとまわり大きなシャーシを用いて普通のトランスを使った方が良かったのかも知れませんが、コンパクトなアンプを作りたいという欲求に負けてしまいました。
少し気を付けなければならないのは、±90Vまでしか許されていない5687のヒーター−カソード間の絶縁耐圧です。 本機では限度近くの±約90VのB電圧が掛かっていますので、出力段のマイナス側のヒーターの電位によっては最大定格を超えてしまいます。 回路図に小さくピン番号を入れていますが、ヒーター用の電源はプラス側を接地して、出力段のマイナス側のユニットのヒーターに−12.6Vが掛かるような配線する必要があります。この点については7044とか7119だと絶縁耐圧が高いので考慮する必要はないと思います。
内部抵抗は中途半端だし、ヒーター−カソード間の絶縁耐圧は低いしと、全くもって5687はSEPPアンプの出力段には向いていないのですが、QRPアンプの要件を満たす球は他に適当なものが見つけられなかったので妥協するより仕方ありません。
実装
 はらわた
はらわた
究極の小ささを目指して(大袈裟!)実装設計を行いました。 使用したシャーシは160mm×100mm×50mmのアルミシャーシ(t=1mm)です。失敗する可能性もあったのと、手作りアンプの会で紹介されているQRPアンプがアルミシャーシの塗装無しが多かったので、それに倣いました。 これが一番安くて早いです! シャーシが小さいので、かなり無理をして詰め込みました。 いつもならいちおう気にする見てくれの格好良さは、今回は全く考える余地がありませんでした。とにかく内蔵物を詰め込むのに苦労しましたが、その分たっぷり楽しむことが出来ました。 QRPアンプは比較的安価にできますし、こういった挑戦にはもってこいのアンプかもしれません。
 3つの小型トランスを内蔵しています。
3つの小型トランスを内蔵しています。
マイナートラブルとしては、5687の寄生発振に遭遇しました。 グリッド抵抗(820Ω)を入れて事無きを得ましたが、さすがに高gm球だけあります。 実装には十分注意を払わなければなりません。
 SW電源を外すと電源基板が見える
SW電源を外すと電源基板が見える
 真空管ソケット部周辺の配線
真空管ソケット部周辺の配線
測定結果
| 周波数特性 | Lch(at 20Hz) | −3.17dB |
| (1V出力、8Ω、1kHz基準) | (at 100KHz) | −3.18dB |
| Rch(at 20Hz) | −2.83dB | |
| (at 100kHz) | −3.20dB | |
| 最低雑音歪率 | Lch(100Hz) | 0.0354%(0.03W) |
| (8Ω) | (1kHz) | 0.0165%(0.03W) |
| (10kHz) | 0.0230%(0.03W) | |
| Rch(100Hz) | 0.0441%(0.05W) | |
| (1kHz) | 0.0263%(0.05W) | |
| (10kHz) | 0.0292%(0.05W) | |
| ダンピングファクタ | Lch | 8.85(1V → 1.113V) |
| (8Ω、1kHz、1V出力) | Rch | 8.77(1V → 1.114V) |
| 仕上り利得 | Lch | 6.34dB |
| (at 1kHz) | Rch | 6.34dB |
| クロストーク | Lch → Rch | −72.21dB(at 20Hz) |
| −75.11dB(at 20kHz) | ||
| Rch → Lch | −75.95dB(at 20Hz) | |
| −77.08dB(at 20kHz) | ||
| 残留ノイズ | Lch | 112.3μV(10〜300KHz) |
| (8Ω、入力ショート) | 8.852μV(IEC−A) | |
| Rch | 192.5μV(10〜300KHz) | |
| 7.822μV(IEC−A) | ||
| 消費電力 | 31.1W(100V、0.372A) |
総括
山椒は小粒でぴりりと辛い、というようなアンプに仕上げることができたと思います。 ただ単に小さいアンプというだけでなく、それなりに測定結果や音がまともな(良いとは言ってませんよ、まともと言ってるだけです)アンプにしたかったので、いちおう満足しています。 半導体回路で真空管をドライブするSEPPは、アンプ回路を小さく実装することが可能ですからQRPアンプに向いていると思います。 ちなみに本機のアンプ回路は、真空管を除いて約85mm×約50mmの基板にステレオ分を実装しています。 後はもう少しSEPP向きの出力管を見つけることが出来たら良いのですが... どなたか良い球をご存じでしたら教えて下さい! 出力トランスにもう少し投資をすれば、音をグレードアップさせることが出来るのではないかと思います。 でも、本機の音も決して捨てたものではありません、コストパフォーマンスは最高だと思います。 騙されたと思ってST−48をお試しあれ! SEPPの場合、出力トランスはインピーダンス変換だけが出来れば良いので、管球式アンプ用のものは必ずしも必要ありません。 探してみたら無いようであるものだと感じました。 本機のように出来るだけ小さくすることも出来ますし、もう少し投資して音を追求する選択肢もあります。
ただ、予想されたことではありますが、あまりに詰め込み過ぎたために、かなり熱を持つアンプになってしまいました。 (まあ、私の作るアンプは程度の差はあれ、どれも同じような感じですから最近は慣れっこになってしまいましたが...) 一つ拙いことがあります。 スイッチング電源をシャーシ内部に逆さにマウントしていますが、どうもこれは仕様書によるとやってはならない事だったようです。 容量に余裕を残していますので、これまで問題は出ていませんが、電源自体がかなり熱を持っています。 あまりに熱くなるので効率を調べるために仕様書を読んで発見しました。 この電源の効率は71%となっていますから、なんと約4.6Wの発熱です。 それがこんな小さなシャーシの内部にあるのですから、なるほどアンプ全体が熱を持つわけです。 スイッチング電源は、これからも真空管アンプを設計、製作する上で活用していこうと考えていますから、今度からは仕様書をよく読まないといけませんね。