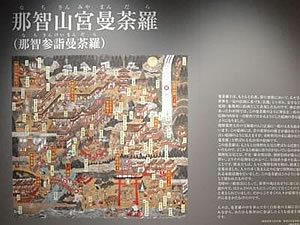| |
|
 |
京都から那智までの道のり
熊野は、古代から「神の鎮まる処」として人々にあがめられてきました。
そして平安の昔から現代に至るまで、時代の流れとともに多くの人々が
聖地巡礼の旅をしてきました。ここでは、13世紀はじめに書かれた
藤原定家の「後鳥羽院熊野御幸記」をもとに京都から那智までの道のり
をたどっていきます。
|
|
| |
|
 |
補陀落渡海
補陀落渡海とは、南方海上にあると想像された補陀落世界(観音浄土)を
目指して船出する宗教行為でした。なかでも熊野那智の海岸は多くの
僧が渡海した補陀落渡海の最大の拠点として知られています。那智参詣
曼陀羅に描かれた補陀落渡海の様子をジオラマ模型で再現しています。
|
|
| |
|
 |
熊野那智大社と那智山青岸渡寺
熊野那智の信仰は、日本一の高さを誇る那智の滝に代表される自然崇拝か
ら始まったものです。熊野三山の中で「熊野那智大社」と「那智山貴岸渡寺」
は、那智参詣曼陀羅に描かれているように、神仏習合時代の姿を今に伝えて
います。ここでは、熊野那智大社、青岸渡寺、那智の滝、大門坂のパネル展示
のほか、3面マルチディスプレイによる那智の火祭りの映像などで熊野那智
を体感していただけます。
|
|
| |
|
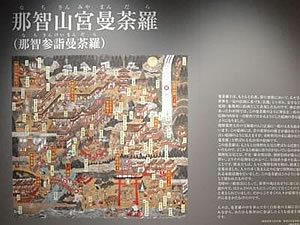 |
那智山宮曼荼羅(那智参詣曼荼羅)
那智参詣曼荼羅は、もともとは熊野比丘尼と呼ばれる尼僧たちが、平安・
鎌倉期以降、熊野信仰が盛んになったのに伴い、その信仰を広めるために
持ち歩いたもので、往時の熊野那智の様子が詳細に描かれています。
熊野那智大社の宝物殿の入り□正面にある「那智山宮曼荼羅」の複製を
展示しています。
|
|
| |
|