| 前編-2 【秋田県・青森県・岩手県】 | |
 |
|
|
 |
 |
|
|
 |
 |
|
|
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
|
|
 |
|
 |
 |
 |
|
|
 |
|
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
|
 |
 |
|
|
 |
 |
|
|
 |
 |
|
|
 |
 |
|
 |
 |
|
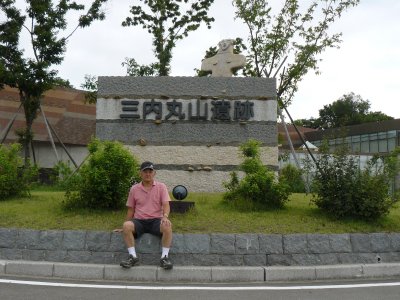 |
 |
|
|
 |
 |
|
 |
|
 |
 |
|
|
 |
|
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
|
|
 |
 |
|
|
 |
 |
|
|
 |
 |
|
|
 |
|
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
|
|
 |
 |
|
|
 |
 |
|
|
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
|
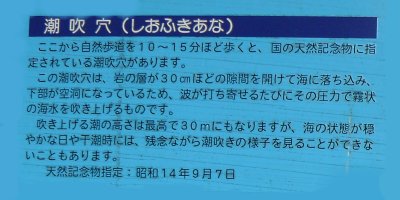 |
|
 |
 |
 |
 |
|
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
|
|
 |
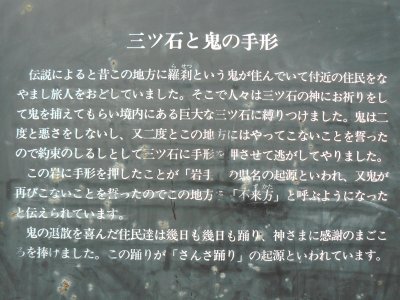 |
|
|
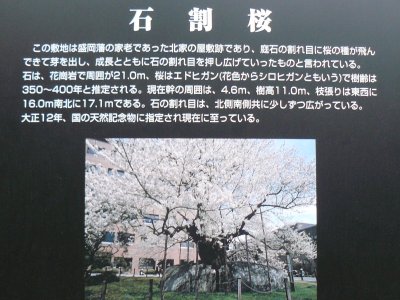 |
 |
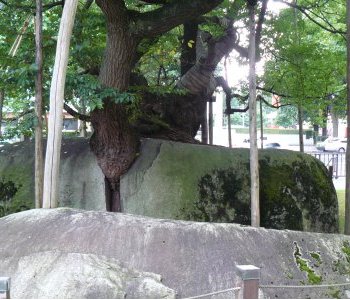 |
|
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
|
|
 |
|
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
|
|
 |
|
 |
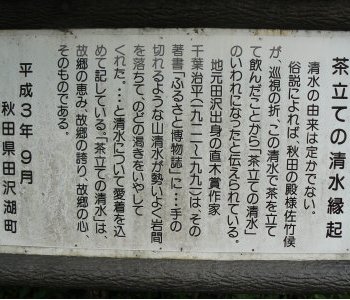 |
|
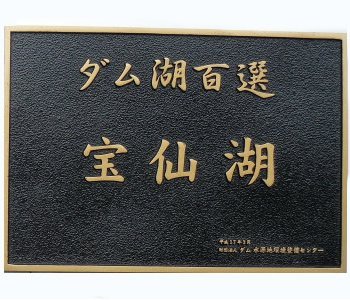 |
 |
|
 |
 |
|
 ハクサンシャジン |
 ミヤマアキノキリンソウ |
 タチキボウシ |
 ノリウツギ |
 |
|
 |
 |
|
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
|
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
|
|
 |
 |
|
 |
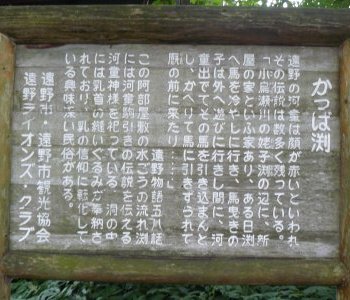 |
 |
|
 |
 |
|
|
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
|
 |
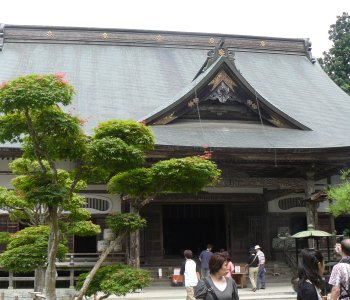 |
 |
|
|
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
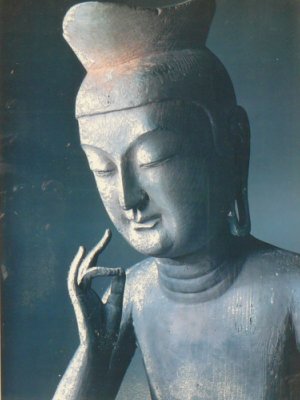 |
|
|
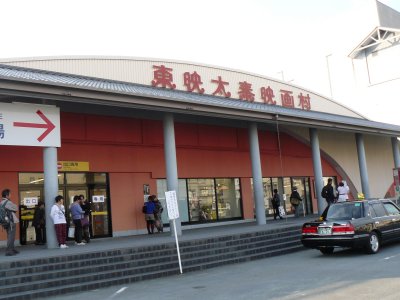 |
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
|
|
 |
 |
|
|
 |
 |
|
 |
| 次は 後編-1 【宮城県・山形県・福島県】 です。 |
| 次の3月20日(木)は 【道の駅、厳美渓・青葉通り・広瀬川】 88 です。 |
| 旅のページへ戻る |