| 06. 山陰道(山口県・島根県・鳥取県) |
|
 |
|
 |
 |
| 06. 山陰道(山口県・島根県・鳥取県) |
|
 |
|
 |
 |
 |
|
|
 |
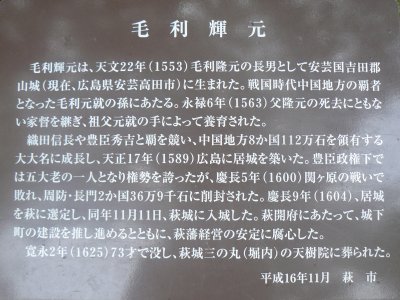 |
|
 |
 |
|
|
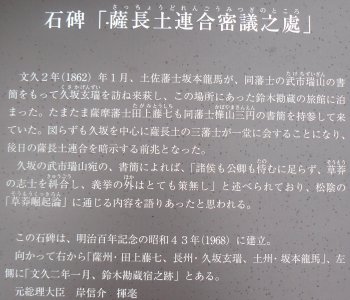 |
 |
|
 |
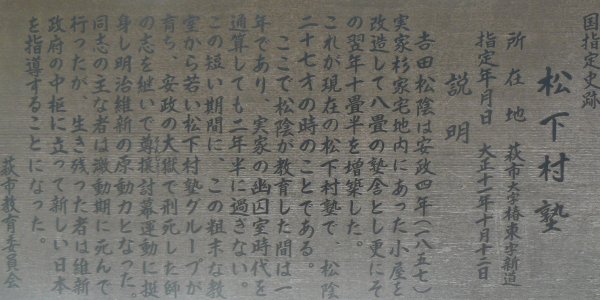 |
|
 |
 |
|
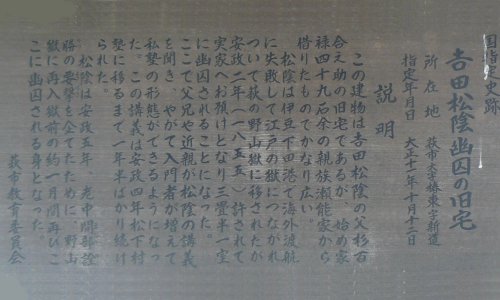 |
|
 |
 |
 |
|
|
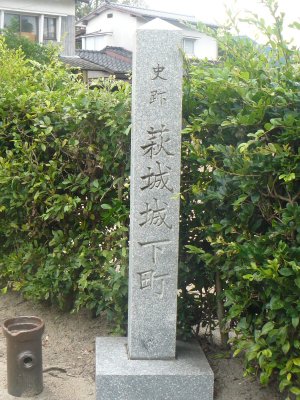 |
 |
|
 |
 |
|
|
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
|
|
 |
|
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
|
|
 |
 |
|
|
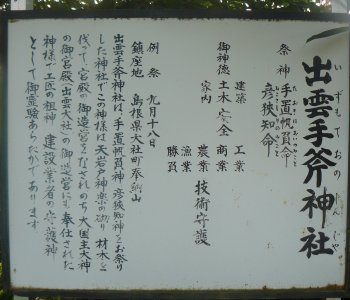 |
 |
|
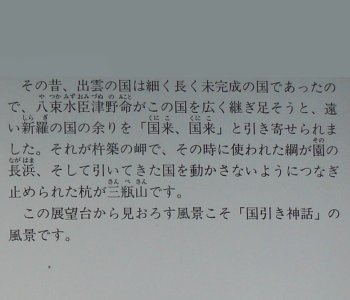 |
 |
|
 |
 |
|
|
 |
|
 |
 |
|
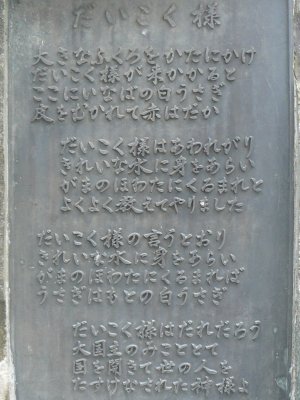 |
 |
 |
|
|
 |
 |
|
 |
|
 |
 |
 |
|
|
 |
|
 |
 |
 |
 |
|
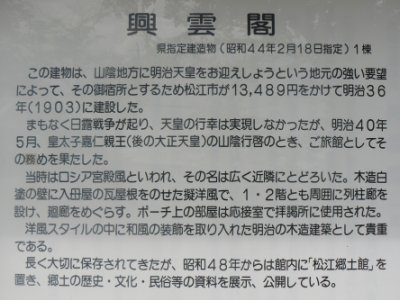 |
 |
 |
|
|
 |
|
 鬼太郎と目玉おやじ |
 のんのんばあとオレ |
 鬼太郎と父さん |
 水木しげる像 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
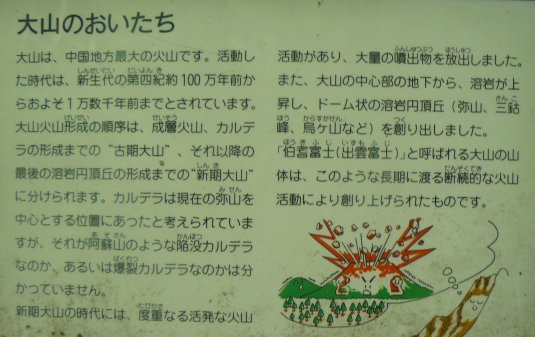 |
|
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
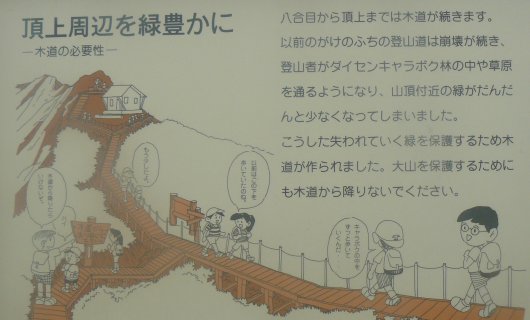 |
|
 |
|
|
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
|
|
 シモツケソウ |
 クガイソウ |
 シコクフウロ |
 ヤマハハコ |
 エゾノヨロイグサ |
 ヤマホタルブクロ |
|
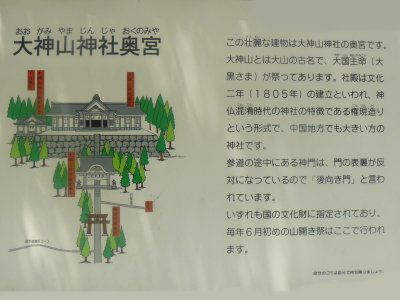 |
 |
|
 |
|
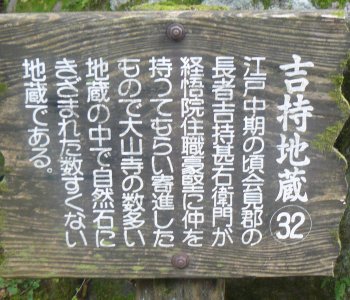 |
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
 |
|
|
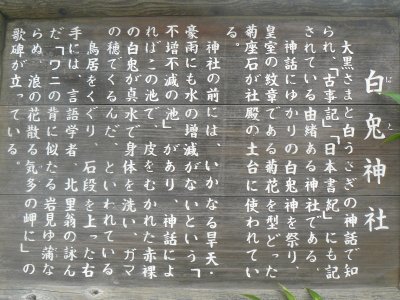 |
|
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
 |
 |
|
|
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
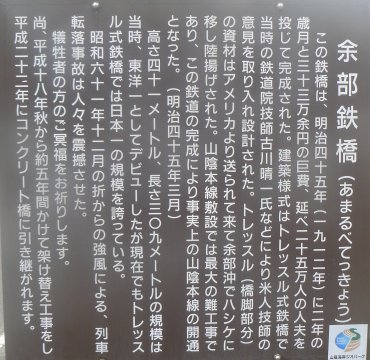 |
|
|
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
|
 |
 |
| 08. あとがき |
|
| 旅のページに戻る |